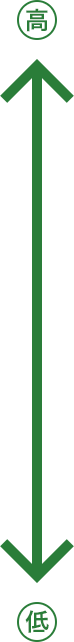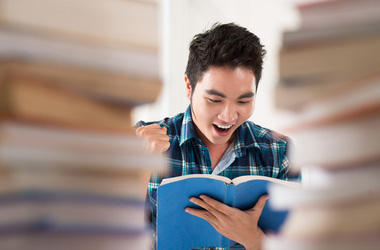日本語能力試験とは?
日本語能力試験(Japanese Language Proficiency Test、略称JLPT)は、原則として日本語を母語としない人の日本語能力を最上級のN1から最下級のN5まで5段階のレベルで認定する試験です。日本を含め世界65カ国の地域で、7月上旬と12月上旬の年2回試験が実施されています(一部の受験地を除く)。日本語能力試験は、年間約60万人もの人が受験する、日本語を母語としない人を対象とした日本語の試験としては、最も受験者数の多い試験となっています。
日本の国立大学への国費留学の要件として日本語能力試験N1が要求されるなど、重要な日本語能力認定基準となっており、日本出入国管理上の優遇措置の考査基準にもなっています。
日本語能力試験の試験方式は、ほとんどの問題で4択(一部3択)のマークシート方式となっていて、日本語を母語としない外国人が外国語として日本語を学習するカリキュラムが基準となった問題が出題されます(日本語を母語としている人が学ぶ国語の学習要領とは異なります)。
日本語能力試験の目安
日本語能力試験には、N1〜N5の5つのレベルがあります。最も難しいレベルがN1、最も簡単なレベルがN5です。N1〜N2では、日本語を使った生活を現実的にしていく上で必要なレベルに達しているかを判断し、N4〜N5では教室や本などで学習する基本的な内容が理解できているかを試験します。N3はN1〜N2とN4〜N5の中間のレベルです。
| むずかしさ | レベル | 認定の目安や基準 |
|---|
 | N1 | | 読解 | - 新聞の論説や評論が読解出来るレベルです。複雑な文章の構成や内容を論理的に理解できるかが問われます。また、様々な内容の文章の行間を読むことも求められます。
|
|---|
| 聴解 | - 様々なシーンにおいて自然なスピードで話の流れや、登場人物の関係性や話の内容などが詳細に理解でき、要旨を把握できるかどうかが求められます。
|
|---|
|
|---|
| N2 | | 読解 | - 新聞や雑誌等の明解で平易な文章を読んでその記事の論旨や内容を理解できることが求められます。
|
|---|
| 聴解 | - 日常的な場面において、自然に近いスピードでまとまりのある会話を聞いて、話の流れや登場人物の関係性を理解し、要旨を把握できることが求められます。
|
|---|
|
|---|
| N3 | | 読解 | - 日常的な話題について書かれた具体的な内容を表す文章を、読んで理解できるかが求められます。
|
|---|
| 聴解 | - 日常的な場面で、やや自然に近いスピードのまとまりのある会話を聞いて、ほぼ話の流れや登場人物の関係性と要旨を把握できることが求められます。
|
|---|
|
|---|
| N4 | | 読解 | - 基本的な言葉や漢字を使って書かれた身近な話題の文章を読み、理解できることが求められます。
|
|---|
| 聴解 | - ゆっくりと話される日常的な会話であれば、内容がほぼ理解できることが求められます。
|
|---|
|
|---|
| N5 | | 読解 | - ひらがなやカタカナに加え、基本的な漢字を使って書かれた短い定型文や語句等を読み、理解できることが求められます。
|
|---|
| 聴解 | - 日常生活の中でよくある場面でのゆっくりとした会話であれば、必要な情報を聞き取り、理解出来ることが求められます。
|
|---|
|
|---|